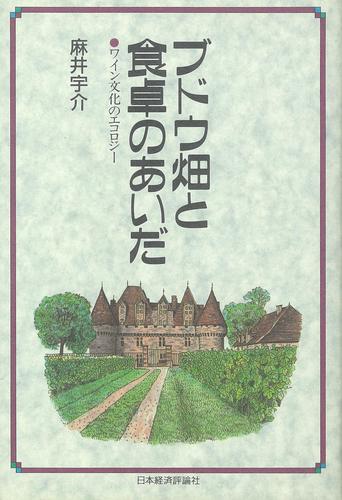 ハードカバーを読みました。
ハードカバーを読みました。
副題で損をしていると思います。
エコロジーという言葉は流行り廃りに
左右された言葉ですし、
本書の内容はあまりエコとは関係ないので…
作者が敬愛する鯖田豊之『肉食の思想』*1の
技法を用いて、
欧州に於けるワインについて
ひとりの日本人として
考察を試みた本だと思います。
今日はいろいろあったので、
あとは後報で失礼します。

- 作者: 麻井宇介
- 出版社/メーカー: 日本経済評論社
- 発売日: 1986/10
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

ブドウ畑と食卓のあいだ―ワイン文化のエコロジー (中公文庫)
- 作者: 麻井宇介
- 出版社/メーカー: 中央公論社
- 発売日: 1995/10
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る
アマゾンの評では、同じことを繰り返して、くどい、
と言われる本書ですが、繰り返さないと、アタマにはいりにくい、
という内容であることも確かかと。
・ワインは水替わり、という発想のもとには、
「水は飲むもの飲めるもの」という日本固有の伝統観念がある。
そもそも水が飲めない風土土壌では、
「水は飲むもの」という概念が育つはずはない。
だから、ワインは酒か水替わりか、という議論は、
それ自体日本を背景とした論争であり、現地の観念としてはナンセンスである。
・葡萄だけを使って作るワイン、日本酒のように水を足して作る酒でないワインは、
飲めない水土壌地域でのかけがえのない水分補給の手段であり、
水によって蔓延する感染症やウイルスの危険性に対しても有効であった。
頁13
いまでこそ銘醸地のブドウ畑は、その産地を代表するブドウ品種が整然と植えつけられている。だが、かつてはいろいろな品種が雑然と混植されていたり、収穫のとき、品種の違うものをまぜてしまうなど、ワインの酒質とブドウ品種の関係を厳密に管理して醸造する考えはなかった。
ボルドーもその例にもれず、赤ワイン用の品種と白ワイン用の品種を混醸していた。その割合が、ロゼよりやや濃い程度の、明るく鮮やかな赤となったのである。ブドウの品種ごとに仕込みを分けて、赤ワインと白ワインが明確になったのは、ボルドーでは一九世紀になってからだといわれている。
・水が飲めるもの、という観念がなく、ワインで煮炊きやのどの渇きを癒す生活については、
池本喜三夫『フランス農村物語』からの引用にて具体的に紹介している。
昭和九年刀江書院の出版物とのことですが、検索すると、昭和19年に新正堂、
昭和46年に東明社から再版されているようで、フツーに古書も見つかりました。
・だが欧州でも水を飲むものと言う文化があることは、『肉食の思想』の著者でもある、
鯖田豊之『水道の文化―西欧と日本』 (新潮選書)1983年から、
ドナウ河がありながらわざわざアルプスの水を水道で送って使用したウィーンの例を引いて、
紹介している。結局、飲用水が廉価で広範に入手可能となった時代以降、
ワインの消費量、質ともに変遷が起こったのであろうという著者の推論。
所謂パラダイム・シフトですね。
・頁76では上記を言い換えて、穀類を主食とし、水を飲む風土文化の日本から、
違った文化が、果実を主食とし、果実を飲む文化であるとしている。
頁38から、テイスティングと利き酒の違いについて述べており、
前者が鑑賞、批評行為で後者が鑑定としていますが、
読めば読むほど、テイスティングは、香道みたいなモンではないかと思い、
もう少し整理してもよいのでは、とも思いました。
ロアルド・ダールの例の『味』とか、香道ですよね、香道よく知りませんが。
頁147
かつて、イギリスやロシアの貴族たちが、銘醸ワインの有力な顧客であったとき、彼らはワインとともにその文化をも摂取しようとした。しかし、この二〇年ほどの間、アメリカをはじめ、ワインが普及しつつある国々の購買層は、彼らの口に合うワインを求め続けたのであった。ワインの伝統性について心ある人たちは、マテウス・ロゼの成功を苦々しい思いでみつめたことであろう。しかし、この新製品は、初めてワインを飲む人たちの心をとらえた。テーブル・ワインとしては甘すぎるドイツ・ワインや、特異な香りが気になる“ランブルスコ”(イタリア、弱発泡性、甘口赤ワイン)の成功もまた、わけ知りのワイン通とは無縁のマス・マーケットが潜在していることを知らせてくれたのであった。
で、その、わけ知りというのも、パラダイムシフトを経て変質しているが、
その自覚はどうなんだか、無自覚かも、という感じではないか、と思いました。
(2015/3/27)