アフリカ旅物語 (凱風社): 1995|書誌詳細|国立国会図書館サーチ
前川健一が今世紀初頭に出したアフリカ本のカバー写真などが、すべて著者撮影で(写真と本文は関係ありません的なもの)それで読んでみました。「エジプト~スーダン~エチオピア~ケニア~ウガンダ/ザイール」を治めた収めたらしい「北東部編」は図書館にないかったので、「中東部編」だけ読破。
今思ったのですが、私ははてなブログであんまり「読破」ということばを使わないです。検索したら、これまでの八年間で使ったのは八回だけ。たぶんこの本の冒頭、湾岸戦争勃発時、カイロに住んでいた著者夫妻(住んだのは1990~1997らしい)の周りに、イキナリ、「アラブの湾岸諸国でペンキ職人として何年か働いては、中東やサハラ砂漠に何ヵ月も出かける、という生活を何年も続けているらしい」水谷さんという男性(ベルマーレの社長ではない)や、カイロ大学大学院で13世紀のイスラム法学者の理論を研究するハッサンという回教徒の名前を持つ日本人で、少女マンガも収集し、プロレスにも詳しい人や、「四〇ヵ国以上ものアフリカの国々をおとずれていた。しかし、長期旅行者にありがちな、投げやりさや、気負い、あるいは疲れはちっともなく、澄んだ、落ち着いたまなざしが印象的だった」前原さんという青年(せいじではない、たぶん)が次々に登場するので、あてられてしまい、それで、自分もこんなに本読んでこましたってんねやで、と言いたくなったのだと思います。とほほ。
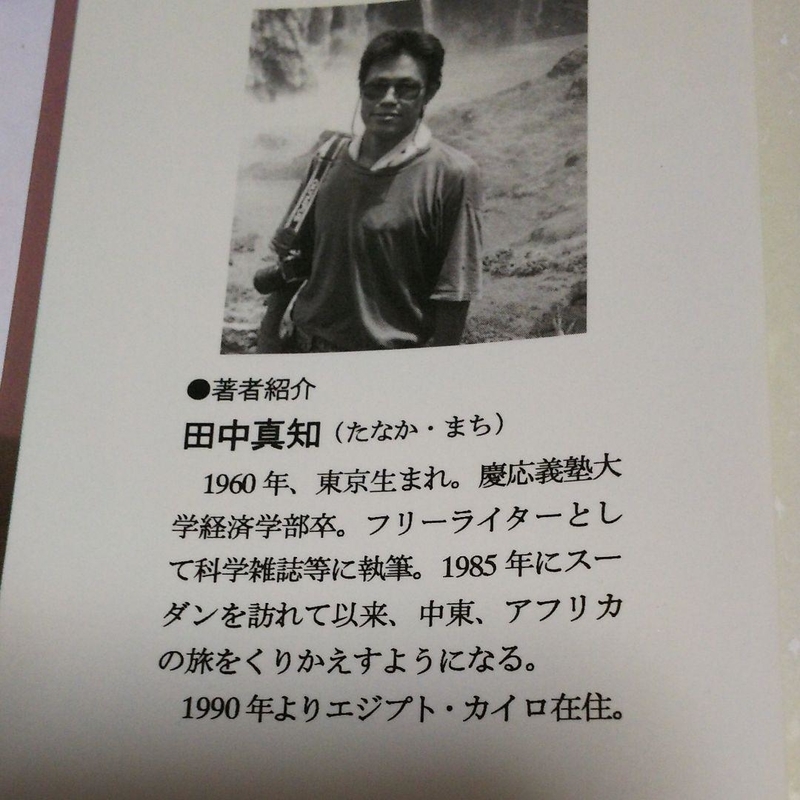
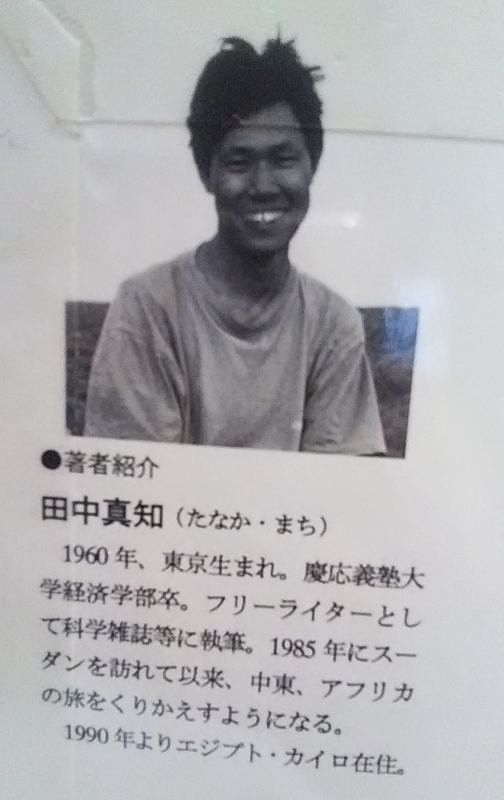
左が北東部編の著者(画像検索で、メルカリで出たもの)右がその後の中南部編の著者。あとの方は、奥さんの意向が反映された気がします。そんでまあ現在がどっちの路線なのか、イベント等の姿は分かりませんが、動画は下記です。
読書イベント?だかトークイベントだかの告知はなべてツイッターで、この動画サイトは、誰か身近に、テレビの芸人よりユーチューバーみたいな児童がいて、それで戯れにやってる気もします。
本書の写真はすべて著者撮影。装幀は蔵前仁一。参考文献あり。版元は潰れてるそうで、ウィキペディアに凱風社の項目はなく、蔵前仁一のツイッターくらいしか情報が出ません。
残念な知らせ。凱風社が破産したらしい。https://t.co/pGLiKeX5xJ
— 蔵前仁一『食べ歩くインド』(小林真樹)発売中 (@Jinichi_Kuramae) 2017年11月24日
それで、本書の旅は、①ザイール(当時)領のザイール川を、星野之宣の鄭和マンガみたいな、フローティングショップハウス連結クーロン城みたいな船で下る。1991年。②その先をしばらく丸木舟で下る。1991年。カヌーとかカヤックが丸木舟になっただけの、水上目線のザイール河下りと言ったら、怒られそうな旅。ユーコン川と違って、熊は警戒しなくていい。③マダガスカルに、ドラえもん六巻か四巻でのび太に似ていると言われたワオキツネザルに会いに行く。1991年。④ボツワナのカラハリ砂漠の真ん中に忽然と出現する湿原、オカバンゴ・デルタにゆく。1994年。⑤ボツワナでブッシュマン考。1994年。⑥ナミビアを、白人数人でランクルチャーターして野宿しながらゆく形式の旅に参加した体験記。それまで白人チャーターの中に一人混じるのはやってなかったとか。1994年。⑦ヨハネスブルグ(マンデラ勝利後)の話。1994年。です。
①ザイールの1991年ということで、私がむかし読んだ高野秀行の処女作『ムベンベを追え』がおとなりコンゴの1988年ですので、思い出しながら比較して読みました。確かコンゴには当時日本大使館もなくて、天理教の教会の日本人が在留邦人のすべてだったような。ザイールはキンシャサの奇跡のキンシャサもあるし、流石にそんなことはないだろうと。いまちらっとムベンベの単行本のほうのアマゾンレビュー見たら、やっぱり予想通り、一言皮肉を言いたい人のレビューがついてました。自己責任の時代、21世紀。
頁34、食用の野生動物の肉のことをブッシュミートと書いていて、これは現在はジビエと呼んでよいのだろうかと思いました。サルやゾウやニシキヘビはジビエか。
頁36
プッシャーボートの三階を歩いていたとき、妻が手すりにつながれたチンパンジーを見つけた。かなり歳をとったメスだった。ほかのサルのように引っかいてこないので、バナナをあげた。バナナには喜んだが、キャッサバをあげると見向きもしなかった。そのときザイール人の若い男が来て、
「こいつは外国では芸をするそうだが、ここでは食っちまうんだ」
と言って、ガハハと笑った。男はいやがるチンパンジーの耳を引っぱって、さあ写真を撮れ、と言った。それから男はチンパンジーをさして、こいつはおまえたちにそっくりだ、そっくりだ、と言ってまたガハハハと笑った。
「失礼なやつ」
彼女は憮然として言った。 (以下略)
ここと、もう一ヶ所、奥さんの写真が載ってます。眼鏡っ子のかわいい方です。たぶん。②には、南国の花を描いたカラフルな水着を着てザイール河で泳ぐ描写もありますが、その写真はありません。載せるかボケ、みたいな。閑話休題。ここを読んで、ふっと、今大坂なおみ選手でホットな、BLM、ブラックライブズマターに関して、それとか多様性とかを批判して与党議員のツイートの「リプ欄が地獄」を演出する方たちについて、「こういう人たちは想像力がない。自分もアメリカに行ったら有色人種で差別される側に回るということに気づいてない」という批判があるのですが、それについて違和感を覚えたのを思い出しました。曰く、米国の人種階級社会は白黒黄なので、黄色人種は白人からだけ差別されるのではなく、その下の黒人からも差別される。黒人から不愉快な目に遭わされた人たちもまた、"Black Lives Matter"に反発しているのではないか、と。
②にはモブツ大統領が1978年当時、イランのレザー・シャー・パフレヴィーに次ぐ世界二位の富豪だった(第三位はイギリスのエリザベス女王)が民衆に支持されていたとか、いろいろ調べてるなーという記述も目立ちます。さすがサイエンスライター。この後のコラムでは、旅のあいだずっとコンラッドの『闇の奥』を持ち歩いて、熱読してたとあります。その辺が、「インドでは石も考えている。だが、アフリカでは石はただの石だ。マテリアルとして存在するだけなのだ」とか言ってボン・シャンカールでおしまいみたいな旅行と違って、だから本で残ったともいえると思いました。
作者は①②に、2012年の同地再訪を組み合わせて再度本を出版しているそうです。奥さんは同行したのか、それ以前にとか、いろいろ知りません。読めば書いてあるのかないのか。
③マダガスカルのキツネザルは人間をこわがらないんだそうです(本書時点)それなのでマダガスカルでは、インドリ・インドリ(キツネザル)はババコト(父なる子ども)とも呼ばれ、そしてそれは進化論と合致するんだとか。いい話だなあ。さすがサイエンスライター。①で、芋虫(マコロコロ)の串揚げピリ辛ソースだれとか、いろいろ珍料理が出ますが、あんまし食べてないので、食レポとしてはあれなので、フードライターとしてはあれなのかも。
④頁151、ランクルツアーが欧米では人気との個所。なんとなくカイラスへのランクルツアーを思い出しました。カイラス、いいとこだよ、一生に一度行くべきだよ、と、知り合いの家に来た、脱サラOLの人からの絵葉書見て、その金とヒマがないからみんな行けなくて憧れの地やんか、と思ったです当時。ボツワナとナミビアは貧乏旅行者お断りなので、バックパック旅行を安くあげるのは至難の技なので、トラック型の車一台チャーターシェアするのが一番安いんだとか。
⑤ブッシュマンについては、柔和なアーモンド・アイの写真が多く、アジア人にも似た顔だちなんだなと思いました。諸星大二郎『ダオナン』は、ほんと、そのまんまなんだな、よく描けるものだ。で、どうしてああいう作品を描こうと思ったんだろう、と、本書のブッシュマンの近代史(優秀な砂漠の狩人としてのソルジャー従軍記と虐殺)を読みつつ思いました。
⑥頁219、ランクルツアー。作者はこれが初めての白人の中に自分一人のオリエンタルツアーだったそうで、意外でしたが、当時は、バックパック旅行というと、白人と日本人、ときたま香港人や韓国人だったなと思い出しました。黒人はその後増加したのかというと、してなさそうですが、日本人以外のアジア人、特に韓国人や中国人の自由旅行者は格段に増加したのではないか。で、こういう時、英語の優劣で、アジア人同士マウントをとり始めることがよくあるので、そういうのもバックパック旅行の日本における衰退理由のひとつと思うです(もともと盛んな時代なぞなかったという人もいるかもしれませんが)白人と日本人だけの海外貧乏旅行の時代が終わり、そこに韓国人中国人(台湾人含む)が陸続と参入する。本書でも、一ヶ所日本人カップル、一ヶ所韓国人夫婦が出ますが、後者は宗教関係者ではないかと勝手に思いました。時代的に。
頁218、アパルトヘイト廃止後の大統領選挙でマンデラが大統領になったら治安が悪化すると言われていたが、本書当時は白人への報復行為は一件もなかったと書いています。しかし、日本のメディアも、当時遭遇したヨハネスブルグからの帰国子女も、口を揃えてアパルトヘイト廃止後は治安が悪くなったと書いたり言ったりしてましたので、一時の平和のあとで、治安は悪くなったのだろうと考えました。が、現地に行くまで、作者はナイロビ等でもさんざん同様のことを言われて脅かされたそうで、現地に行ってみて、現地生まれ現地育ちのユダヤ人や後述の邦人などとは会いましたが、犯罪にはあわず終わったということで、ヨカッタデスネと思いました。
頁221
けれども、ナミビアという国は、そうした「白人」旅行者にとっては、たしかに楽しい場所にはちがいなかった。町には、ドイツの植民地時代の名残である瀟洒な北方風の建物、焼きたてのパンを出すジャーマン・ベーカリー、おいしい生ビールや本格的なチーズなど、欧風の快楽をしっかり残しながら、そのまわりに、変化にとんだ稀有なスケールの自然を配している。アフリカでもっともゆたかと言われる動物保護区であるエトーシャ国立公園、世界でいちばん美しいと言われるナミブ砂漠、アメリカのグランド・キャニオンにつぐ大峡谷と言われるフィッシュリバー・キャニオンなど、世界でもなかなか類を見ない景観に、ここほどめぐまれた土地も珍しかった。しかも、ブラック・アフリカにつきものの、うんざりさせるような手続きとはナミビアは無縁だ。あらゆることがスムーズにすすむ。そんなわけで、白人バックパッカーのあいだでは、ナミビアはとくに人気の高い国のひとつだった。
私には、どこの植民地かも分からない、地図上の空白地帯でしたが、ところ変わればというところでしょうか。
⑦頁258、ヨハネスブルグの繁華街ヒルブローの描写で、道端では台湾人らしき男が安物の時計や電卓を売っていたとあり、ああこの頃はまだ南アは中華人民共和国でなく中華民國と国交を結んでいたなと思いました。この数年後ですが、南アにいたことがあるという中国人と、キンペーチャンの第二の故郷のほうで会ったことがあり、こっちが何も言わないうちに、「皆まで言うな、言いたいことは分かる。確かに南非は我が国と国交はない、だがこれこれこうすれば入境証が発行されて入国出来るのだ」と言われたのを思い出します。
頁259、大阪の建設関係の労働組合勤務で、三ヶ月の休暇をとっては、中国なりインドなり南米なりへ旅行する人が、今度は南アに来てる人に逢います。作者はカイロで日本の組合旅行のゴルフ三昧を見て、密かに軽蔑してるのですが、この老人には敬服します。しかしこの組合専従の人が、釜ヶ崎でも日当一万三千円なので、世界の貧困とはだいぶ違うと言っているのは、その通りだと思います。工場でも何でも派遣になって、現場にも外国人が入ってきたのは、小泉政権と竹中平蔵の成果と誰かが言ってましたが、はてそれであってますのかどうか。
で、その組合勤務の人は、釜ヶ崎支援の初期に仲たがいした先輩がいて(元京大生)その先輩が本書時点でジンバブエ現地在住の研究者になっていて、遺恨を水に流して前に進むためにアフリカに来たとかなんとかだったそうです。ここで、釜ヶ崎と山谷は成り立ちから何までいろいろ違うのに、「ドヤ」でひとくくりにするのはどうかという疑問が呈されていて、いやいっしょだろ、知らんけど、と思いました。寿も含めて、マトリックス形式の比較一覧表でも作ってほしいです。
エピローグで作者は、二十代から三十代へかけてのこれらの旅行について回想し、丸木舟を降りた時、何か、青春と呼んでいいのか分かりませんが、何かが終わったと感じたそうです。そうした日々ももう、四半世紀前ですか。現在は、スマホと中国資本の大陸となり、野生動物なんかは、数が減って、本書で書かれるような乱獲状態ほど獲れなくなってる状況下で、ガバガバ獲れた時代の写真も記述も意味があると思います。
エピローグの最期は、飛行機事故でなくなった共同通信ナイロビ支局長沼沢均という方への冥福の祈りで終わっています。以上
【後報】
21世紀は通信の発達で、現地情報の入手もオンラインダイレクトですし、悲惨なものでなく(それも大事でしょうけれど)鰻を探すにょろり旅とか、サバクトビバッタのウルドとか、そういった方面に活路を見出したものが好まれているようにも思いました。どうでしょう。以上
(2020/9/18)
