装幀 菊地信義 写真 著者 まえがき代わりの「送り火」とあとがきあり。巻末に「ミャンマー」ではなく「ビルマ」を使用する旨但し書きあり。東海大学の教育研究所から現在も出ていて、東海大病院やそこの調剤薬局にも置いてある月刊誌「望星」に1997年4月号から1999年3月号まで連載した「根の国への旅」に加筆訂正したとの由。
参考文献は三冊。①著者をビルマにいざなった先行取材者、竹田遼というジャーナリストの方の著書。手近な図書館に蔵書なし。②検索すると、同名の屋久島ガイドの方が出るのですが、その人かどうか分からない人の自費出版書籍。③著者がカチン人(本書表記にならって、「カチン族」でなく「カチン人」と記します)に辿り着く前世話になっていたパオ人についての洋書。"PA-OH PEOPLE" by Mika Rolly, Pa-Oh National Organization.
Pa-O National Organisation - Wikipedia
Pa-O National Army - Wikipedia
『森の回廊』『宇宙樹の森』に続く、北ビルマ辺境紀行三部作の完結編もしくは送り火のような作品といえそうです。前川健一がその1999年9月刊行の著書『アジア・旅の五十音』(講談社文庫)は本来吉田敏浩に書いてほしかったが、書かなかったので自分で書いたとしていて、本書はそれに対応するように思います。ひとつひとつのことばをキーワードにエッセーを綴ることを前川健一が勧めたとしたら、吉田敏浩は現地で会ったひと、ひとりひとりについてエッセーを書く方法を選択したと。
新井一二三の『台湾物語』のほうを先に読み終えたのですが、そっちは買った本ですので、いつまでも手元におけるので、こっちを先にあげます。といいつつこっちが後になりました。
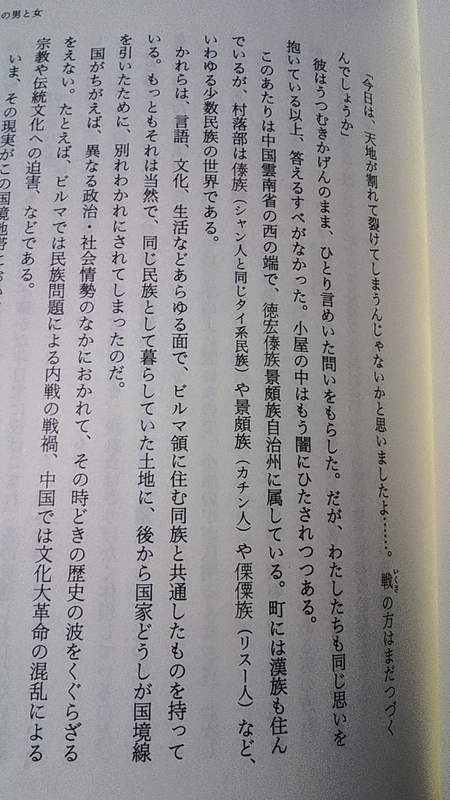
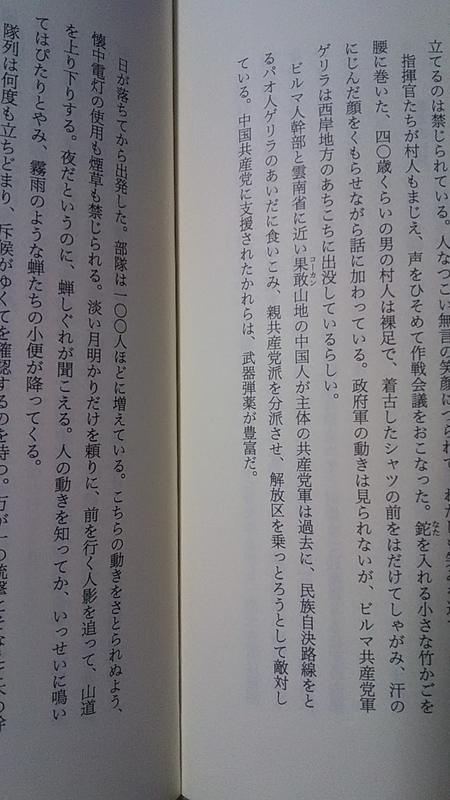
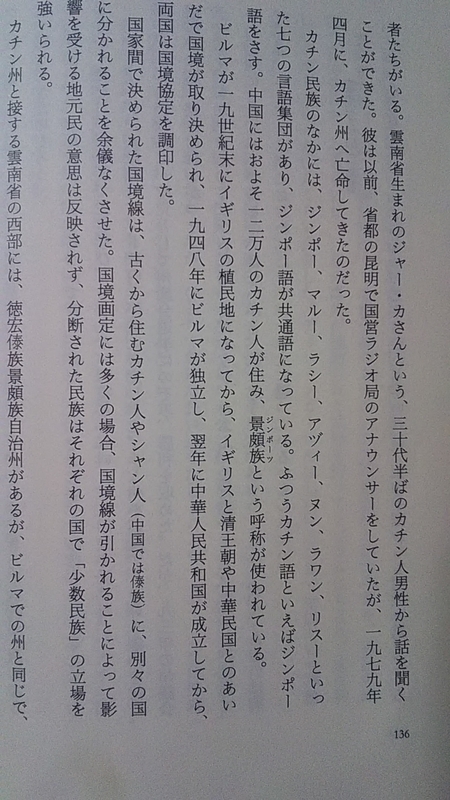
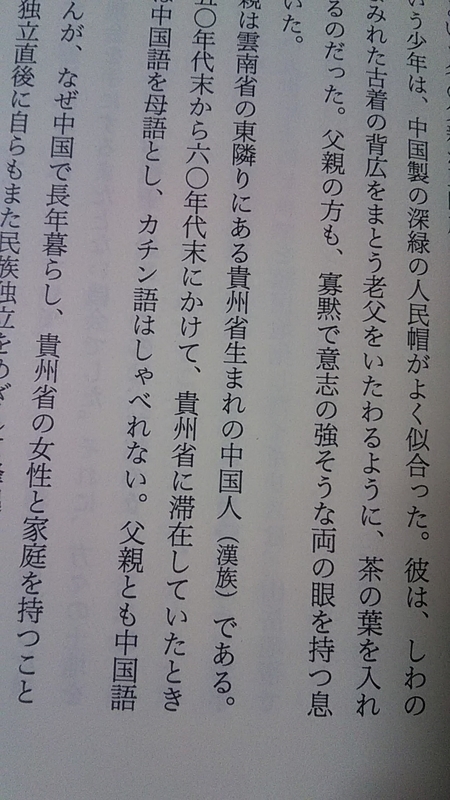
左から、①頁21、②頁74、③頁136、④頁141。
「カチン人」が雲南省のジンポー族であることが分かるのが①頁21。カチンの中に大別して七つの言語集団があり、その中で最大?というか共通語になってるのがジンポーなので、中国では<景颇族>と呼んでいるという説明が②頁136。
雲南側の観光衣装と、本書に登場する民族ゲリラ及び山地焼畑農耕民のなんと違うことよ。というか、時代も1980年代と現代とで、三十年以上隔たってます。
後者のページは同時に、中国からのカチン人亡命者を紹介してます。文革後期から改革開放初期には国営ラジオのカチン語放送アナウンサーだったが、「革命」「国际主义」「主席」など政治用語はそのまま漢語を使い、カチン語に折りこんで放送せよとの慣例を疑問視し、カチン語に翻訳して放送したところ、漢族同僚から孤立し、同僚たちの大漢族主義を批判し、華国鋒に直訴し人民日報に掲載されたことから、主義主張は認められたが、危険人物として地元公安からマークされるようになり、結局1979年4月にビルマのカチン州に逃亡したという話。
これ、後発の高野秀行『アヘン王国潜入記』で、彼が潜入したワ州のワ人たちになると(高野はワ族と書きますが、本書の書き方に従って「ワ人」と書きます。いや、それは私の勘違いで、高野も「ワ人」「シャン人」「コーカン人」と書いてました。すいません)国境を越えたビルマ側ですが、ビルマ共産党支配地域だったこともあり、中国共産党の影響を強く受けていて、政治用語は漢語、北京語をそのまま借用しています(同書頁32「外交部ワイジャオブー」「部長ブーチャン」ほかのページ「文化程度ウェンホワチョンドゥー」「中央チョンヤン」「解放ジエファン」「革命グーミン」「歴史リーシ」etc.)これが政治用語でなく一週間の曜日みたいな生活用語なら、チベットだと隣接する四川方言、ウイグルだとやはり隣接する西北方言の借用になるように思います。雲南省農村部は西南方言なのですが、テレビラジオで話されるような政治用語の借用ですし、雲南省でも例外的に省都昆明は東北もかくやのキレイな普通話を話す人が多いので、なんとなくワ州の漢語もビャオジュンな北京語の発音でそのまま借用しているようなイメージが私の中ではあります。
頁74は、北ビルマの少数民族がビルマのイギリスからの独立後叛旗を翻したのは、低地ビルマ人中心のビルマ政府とその同化政策に反発したから、となっていて、しかし同時に、中国共産党に支援されたビルマ共産党の農村部への浸透とも闘わなければならず、それは、ビルマ共産党がプロレタリア独裁を掲げて、少数民族組織からリーダーを追放して党員をかわりに組織の中心に据えようとする蠢動策謀を常にたくらんでいたからだそうです。土豪列紳といっても、焼畑社会ではそれほど貧富の差が生じず、世代間継承もされないので、共産派の言ってることとやることが違うヘゲモニー掌握のためのやり口が、天然のリーダーに従う共同体社会の民族派と対立し、そして共産派は追われたということだそうです。そもビルマ共産党もまた、低地のビルマ人主体で、少数民族は捨て駒としか考えていないのが透けて見えたとか。
④は奇貨居くべしで避難した中国側で養われ、禄をはんでた人が所帯を持ち、所帯ごとビルマに里帰りして、というくだり。中国最貧困地帯貴州なので、嫁さんもかなりカツカツのおうちなのだろうと思いました。ので、文句ひとつ言わずついてくるとか。そういうことで引用しようと思ったのではなく、作者も、中国内民族はカチン人をジンポーツと書くなど、「族」と書くのに合わせ、漢族を漢族と書いてるんだな、という気づきのメモで置いてます。漢人ではない。漢族。
養われない大規模難民が発生していたこともあり、頁45に一万数千人のカチン人が国境を越えて中国領内にいた時期のことが書かれています。改革開放初期。中国は黙認して追い返したりはしなかったが、援助せず、難民認定もしなかったので、国連の難民高等弁務官事務所(UNHCR)も国際NPOも何も出来なかったとか。ほそぼそと中国側の同族の情けで空いた土地に雨露をしのぐ仮小屋をかけて住み、いろいろ明後日食べて、ときどき密境して自分の畑に収穫に行き、その行き帰りに政府軍に見つかって撃たれて当たると負傷したり死んだり。
けっきょく数世代に渡る内戦の疲労が大きくて、最後は懐柔や停戦になるわけですが、なんというか、複雑ですと思いました。
頁95の戦略村は、中国では、日本軍がやったのより、国共合作前の内戦時代に国府が清郷作戦だか清野作戦だかでやったのが大きいと私は思ってます。なんしかひっくるめて日本扱いになってるような。日本軍の現地部隊に郷鎮レベルの行政をつかさどる余裕や関心があるのかなあと。
そういうもろもろを書くわけですが、十年経っての回想であり、直面した時と違い、時間薬を経て整理された感情を書くわけで、逆に、ぐるぐる回る、どうどうめぐりのループ思考が進行してることも伺えます。現実が、いいほうにいいほうに進んだのならいいのですが、この時点だと、曖昧かな。けっきょく中国がゲリラ援助を飛び越えて、軍事政権じたいを取り込んで海の港に人民解放軍艦艇が寄港するとこまでの、パクス・シノワが実現したと思ってるのですが、ちがうかな。作者が現在それについてどう思ってるかは、知りません。
参与観察のパラドックスの究極版だと思いますが、ゲリラに同行することにより、ゲリラ側に負荷が発生し、平和な地域から拠点までの送り迎えの最中に敵のアンブッシュがあったりすると、被害も出て、死ぬ兵士もいるわけで、それは、ジャーナリストが同行を試みなければそうならなくて済んだのではないか、との自問が取材者の胸中に宿るのだ、と、強く読んでいて思いました。作者は十年経って、十年前のことを始終そうやって考え、ループして舞い戻っている。
ことに作者は現地でマラリアにかかって長期間苦しみ、死の淵まで行き、かなり貴重なキニーネやらなにやら使ってもらい、最後はシャーマンの祈祷により、黄泉の国から帰還するので、その神秘体験と、熱病による幻覚、現地にかけた負担が三位一体となって自問自答を繰り返したのだろうと思います。
もともとの連載タイトルに「根の国」とあるのはそれを意識してると思うのですが、私が見ると、「根の国」=「死者の国」ですから、ひょっとしたら、作者は、若い根っこの会かなんかのポジティヴなルートビアと混同してたのかもと思いました。ハレ、ケ、ネ、の概念は、私の場合、半村良のSF小説『産霊山秘録』で知った付け焼刃です。単行本の題名は、海外華僑の四文字熟語の「落葉帰根」なんかの「根」という概念を取り込んだともいえそうです。
思うに、ベトナム戦争以来、現地が、こんなにジャーナリストに親切だった時代というのも、このくらいまでで、IT革命、インターネットやEメールの登場により、ゲリラや狂信的な連中が自分自身のメディアを持つようになってからは、既成の報道媒体に自分とこをよく言ってもらう必要もなくなり、逆に悪い点を言いふらされるから、攻撃対象になったとすらいえると思います。ベトナム戦争時代、既にしてカンボジアのクメール・ルージュだけははっきりその傾向があり、ベトナムのベトコンや北正規軍、ラオス愛国戦線(パテト・ラオ)と同じつもりで(当然庇護対象になると思って)取材に行って、ロバート・キャパも一之瀬泰造もあぼーんだったわけで、そういうのがアフリカにもあったわけですが、それが普遍になったのが21世紀ではないかと。積極的に攻撃しなくても、末端の連中が小遣い稼ぎに強盗したり、人質にとって身代金要求しても、組織の看板に傷がつくとか心配しなくなった。黙認になったというか、おおっぴらにやるようになったというか。
本書で作者は死体写真を接写で撮ってる時、ふと視線を感じてそっちを見ると、部隊の指揮官の、少佐かな、すごい目で睨まれていて、それが忘れられなかったそうです。たぶん上下関係だったらパワハラされていただろう。客人だから、ガン飛ばすだけで終わった。
本書を読むと、低地のビルマ人は上座部仏教で、山地少数民族は英領時代に宣教師がかなり入り込んだので、キリスト教とアニミズムの併用とあり、それで、ジャーナリストにより、少数民族の村が虐殺されるなど、センシティヴな、「国際的に人権の面で非難を浴びる」事案がひんぴんと明るみに出る時代が作者の滞在時期までで、これって、東チモールによく似た構造と思いました。東チモールは中国から遠かったので、欧米の思惑通りになりましたが、ビルマは中国というファクターが勝った。
以上です。
