お前はただの現在にすぎない : テレビになにが可能か (朝日新聞出版): 2008|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

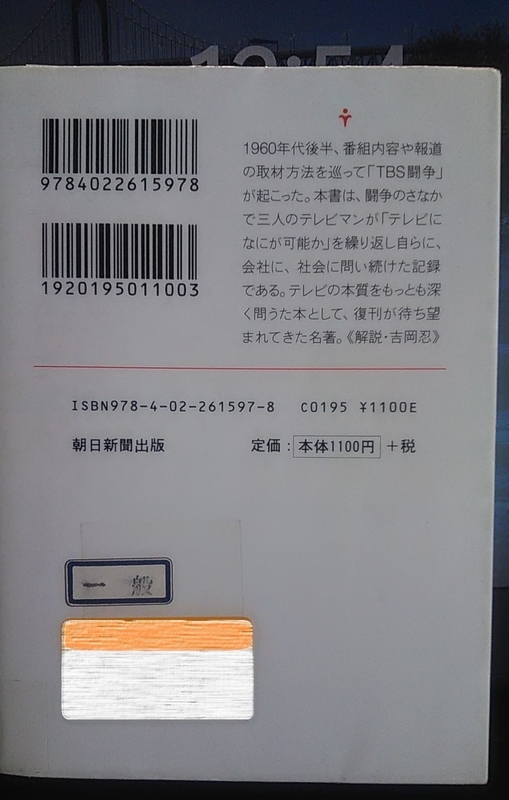
カバー装幀=長井究衡
ホザケンのオジサン、小澤征爾自伝を読んだら、コレの著者のなかのひとりの、萩元サンが解説を書いていて、それが実にクールだったので(のちのN響フリクションにもつながる、ホザケンオジサンの自意識過剰を戒めている)その人の代表作も読んでみました。したっけ、共著で、これもまたはなはだ自意識が過剰な本でした。
序文「文庫版によせて」は立教大学メディア映像論講師(当時)石井信平
解説は山口文憲サンの本にもよく出てくる、ベ平連の中心人物、吉岡忍
文庫化の時点で、著者三人のうち二人は既に鬼籍に入ってしまっていたそうです。
テレビ・今も 「お前はただの現在にすぎない」か - NHK
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/domestic/pdf/050201_01.pdf
Maekawa MemoNo109.2008.11.1
[私的解読・・・「存在論的・テレビ的」]続・「お前はただの現在に過ぎない」文庫版について
ちゃんと読んでませんが、三里塚闘争でプラカード持った農民婦人部隊を放送車に同乗させて機動隊の検問突破かなんかしたのかな、プラカードは板をはがせば角材で、立派な戦闘具材になるので、TBSは極左シンパだなんだとあることないこと書かれたり自己批判しろとかしないとか総括せよとかしないとかあれこれやりもって、クビになったのか自主退社したのか忘れましたが、テレビマン・ユニオンという会社を立ち上げたという、フワちゃんあたりのバイリン芸人が見たら、なんでカンパニーなのにユニオン(組合)なんて名前つけちゃってるのと突っ込みたくなるであろう事態をチェコがどうのなにがどうのと実験的番組の数々とともにただひたすら文章をラレツした本です。緑魔子のインタビュー番組を持ち上げていても、たぶん現存してないんだろうなあとか思いながら読みました。ワダベンだけ分かった。
今のコメント機能のついてるつべの、イヴァン・イリッチも想像出来なかったであろう双方向のコミュニケーションツールぶり(その衆愚ぶりというか、なにがどうしても人類がニュータイプⒸ富野由悠季にならない限り、悪貨が良貨を駆逐する性悪説原理主義のシステムは不変)から見ると、まさに室町時代のメディア論てな感じですが、室町時代ではなく昭和です。こういうの読むと、ものがたりに仮託して考える、『波よ聞いてくれ』のラジオマンレーゾンデートルとか、佐々木倫子の北海道テレビを舞台にしたマンガとか、重版出来の出版社おしごとまんが風景などのやわらかさ、読者を過度につつかない謙虚さって、ほんとうにいいなあ、それなりに人はコミュニケーションを進化させてきてるともいえるのではないかなと思いました。
もともとは1969年3月に刊行された本。
以下目次抜粋。
序章 11
疾走してるときはね、沈潜してる自分を想うでしょ。あるいはその逆。自分のことを書くってのは、どちらでもなく、なんかこう無重力状態だね。不快にして愉快。(今野)
一九六九年三月、私の内側で何かが確実に死んだ。さようなら、私の青春。さようなら、私のTBS。私の内なるおまえにわかれのことばを贈ろう。(村木)
己の過去をふり返るとき、不思議にチェーホフの「中二階にある家」の最後の言葉が浮んで来るんだ。――ミシュース、君はいまどこにいるの?――(萩元)
この序章は、お三方の「私の履歴書」です。私のゐた・せくすありすではなく。
Ⅰ章 お前をチラと見たのが不幸の始まり(太宰治)
3.10成田事件をめぐるドキュメント
お前……
さめた狂気
さめて熱い愛
さめて熱い意志
さめて熱い表現
さめて熱い行為
……テレビジョン
こんなこと目次に書いて、誰が読むんだと思いましたが、目次だけ読んで今北産業にしてしったかでペラペラしゃべる野郎をけむに巻こうと思ったのかもしれません。
Ⅱ章 倒錯の森の中で……(サリンジャー)
4.24中断されたティーチ・イン
社内ではひとりひとりの思想調査がなかば公然と行われ、レッテルはりが始まった。「代々木」「同シンパ」「マスコミ反戦」「同シンパ」「トロツキスト」等々。会社も労組もペタペタ、ペタペタ。
密告と恫喝の季節。
ティーチ・インの中断を許した私たちの前にあるのは、本当に荒地ではなく倒錯の森なのだろうか。
その緑が見えるか? 本当に見えるか?
シールズだった人も今大変だそうですが、それは双方向コミュニケーションツールの発達というか、それに匿名性が付与されてしまったがゆえのいらん摩擦だと思っています。匿名は郵便や電話でもあったことですが、情報量が飛躍的ニーということなのでしょう。
Ⅲ章 八月はいじわるな月(エドナ・オブライエン)
フランス・日大芸術学部・チェコにおける言葉の解放のドキュメント
「政治」っていうのは、何だか涙を誘う。
証拠があるわけじゃないさ。
八月、なぜ妻の目から涙があふれたのか、南伊豆の妻良の海辺で。ベートーベンのピアノ・ソナタと生理日とトランジスタラジオからの「チェコへソ連軍進駐」のニュース。
六月、「いま学生たちがバリケードを築きはじめました」と電話してきた女の人の声にも涙が湿っていた。長髪の細いズボンの学生たちが陽気すぎる仕草で机や椅子を造型していく。バリケードは涙を流さなかったってさ。
Ⅳ章 九月のクロニクル(ポール・ニザン)
10.21新宿、12.24アポロ8号、1.19東大と続くTV中継の陰のクロニクル
村木 私はテレビジョンに別れを告げられるだろうか。
萩元 シュバビルバルラシュバルビル――
今野 一回性を永遠性に、などということは考えない方がいいのかな。
村木 私は私の腐蝕に堪えられるだろうか。
萩元 ダダディドドディダデドゥデダダドウ――
今野 ぼくらは可能性について語りすぎたんじゃないのかな。むしろ不可能性をこそ……。
村木 私は私の内なるあなたを許せるだろうか。
萩元 ……(ブレイク)
今野 自己の位置測定をする作業ってのは大切だけど、その結果を告白するってのは?
村木 私は新しいあなたに出会えるだろうか。
萩元 ズッパリズラズリズラリラズ――
今野 笑い転げたことあったね、三人で。何でだっけ? とにかく際限もなくさ……。
目次で鼎談というか、ダダ会話(あたかも自然な会話をしているように見せて、各人のことばはひとことたりとも意味のある連続性を持ってはならないというゲーム)というか。
Ⅴ章 テレビはジャズである
(初めて引用でない章題を持ってきたところで、以下略)
こんな本で、本のタイトルの「お前はただの現在にすぎない」じたいがトロツキーの文章からパクって、いな、もってきた言葉だそうで(頁491)
頁491
「降伏せよ、哀れな夢想者。お前が長いあいだ待っていた二〇世紀、おまえの〈未来〉であるこのわしがやってきたのだ」。
「いや」と卑下することを知らぬ楽観論者は答える。「おまえは――おまえはただの現在にすぎない」(I・ドイッチャー編、山西英一訳「永久革命の時代」より)
下記の本の下記の小文です。
永久革命の時代 : トロツキー・アンソロジー (河出書房新社): 1968|書誌詳細|国立国会図書館サーチ
- 楽観主義と悲観主義について―二十世紀について、その他多くの問題について / p46 (0028.jp2)
この文章の原文がネットに落ちてないか探しました。ありました。
Л. Троцкий. О пессимизме, оптимизме, XX столетии и многом другом
- Смирись, жалкий мечтатель! Вот я, твое долгожданное двадцатое столетие, твое "будущее"!.
- Нет! - отвечает непокорный оптимист: - ты - только настоящее!
で、この、ты - только настоящее! をこの読書感想の題名にも貼り、英語も貼ろうとグーグル翻訳したのですが、かんばしくない結果でしたので、貼るのをよしにしました。

リアルだと、現在って意味じゃないですよね。なんしかそぐわなくなった。
いちおうグーグルAIの日本語訳も貼っておきます。

さらにそぐわなくなった。トロツキー(虹色)が悪いのか、訳した人(AI)が悪いのか、お三方が道化になってしまっているのか、分かりませんが、ここで筆を置きます。以上