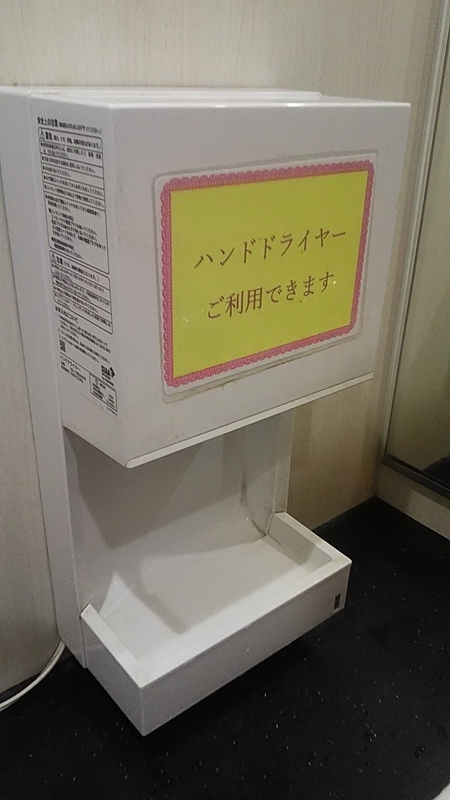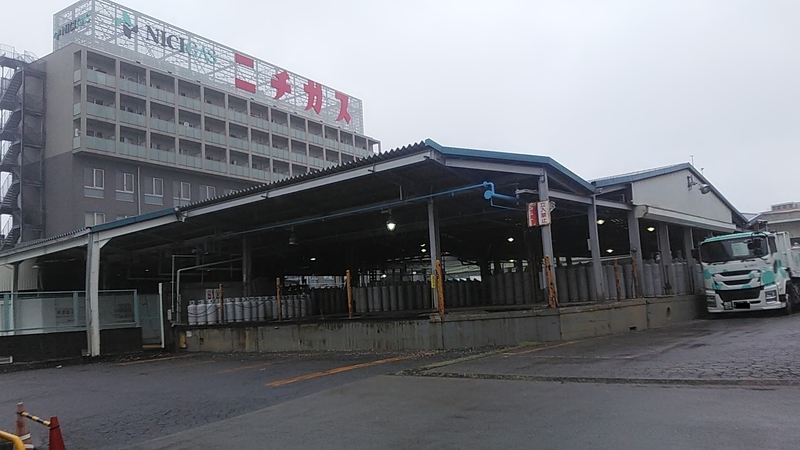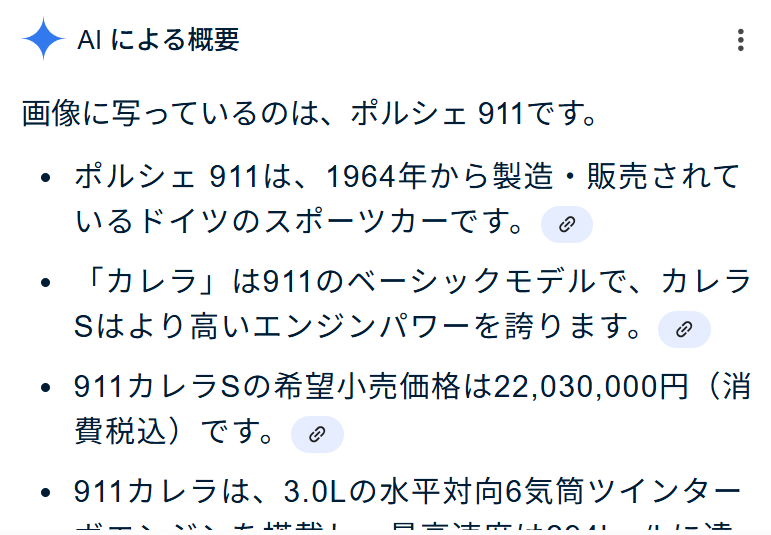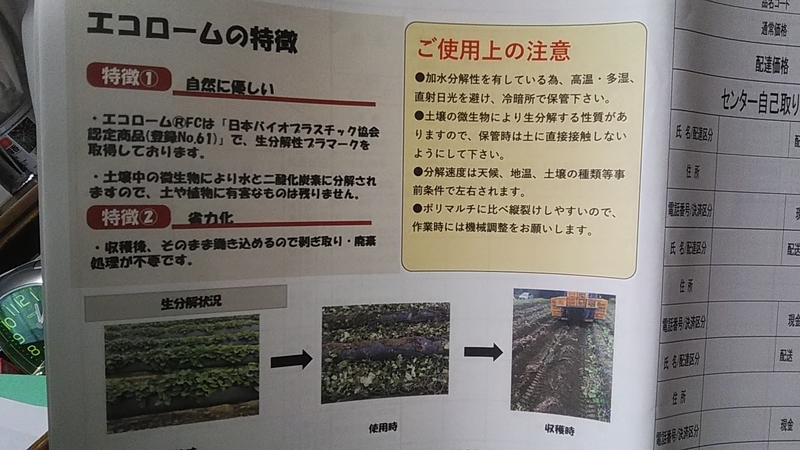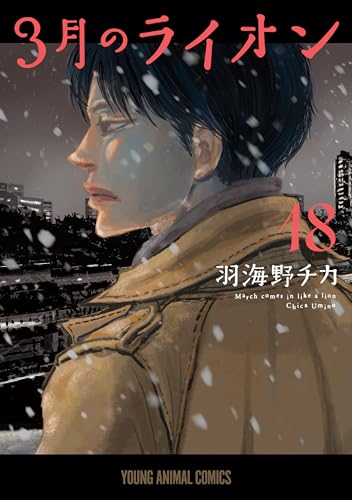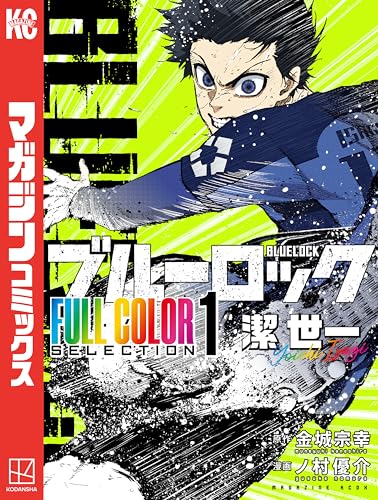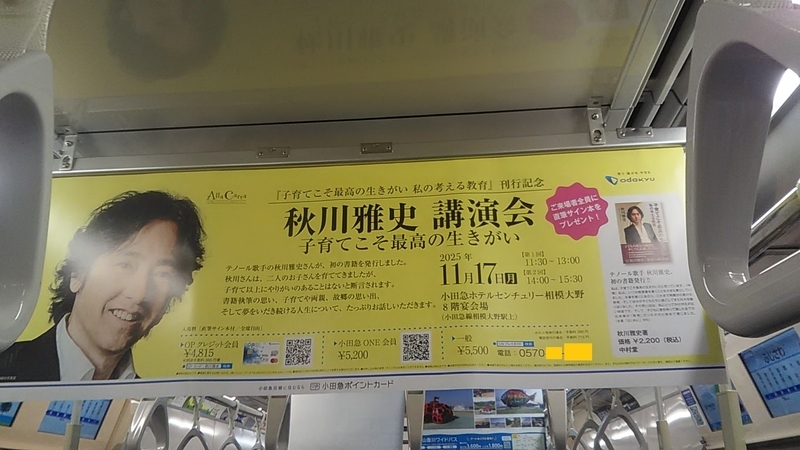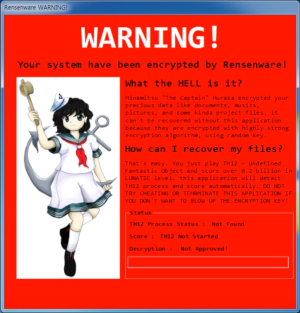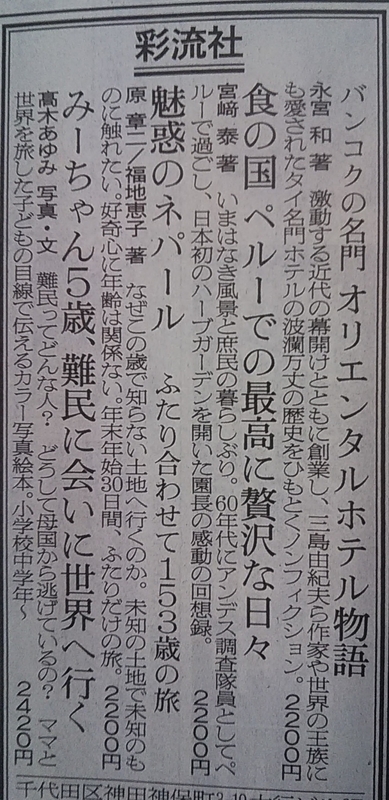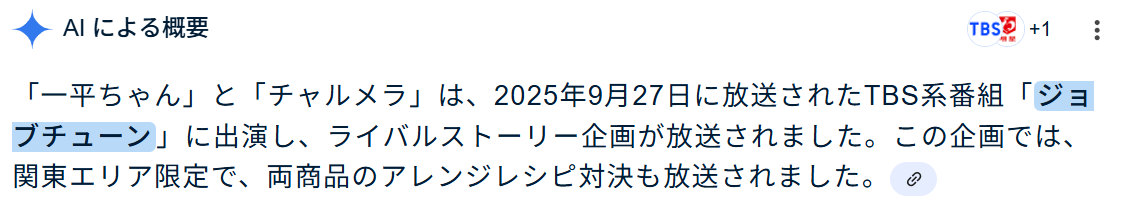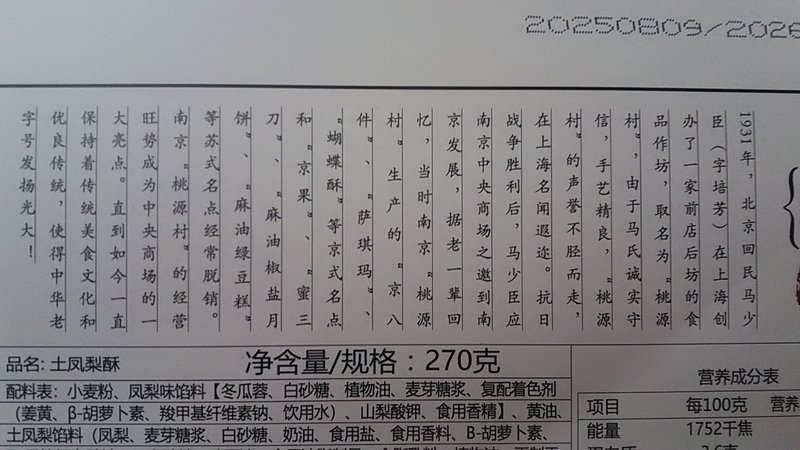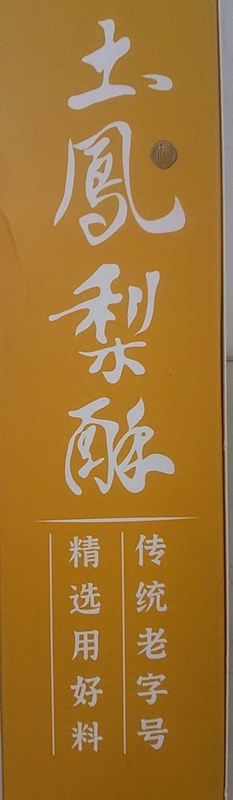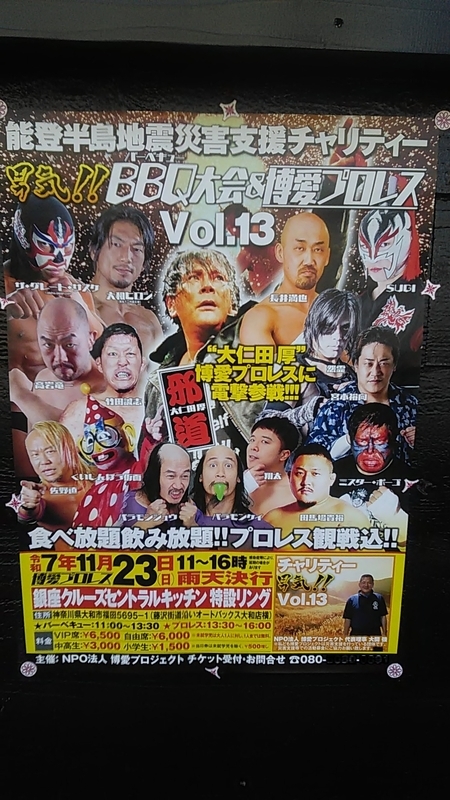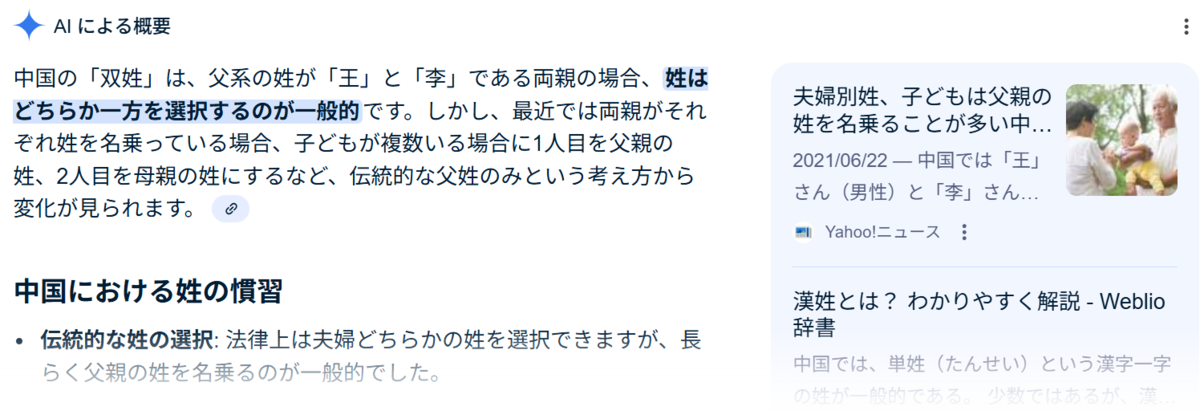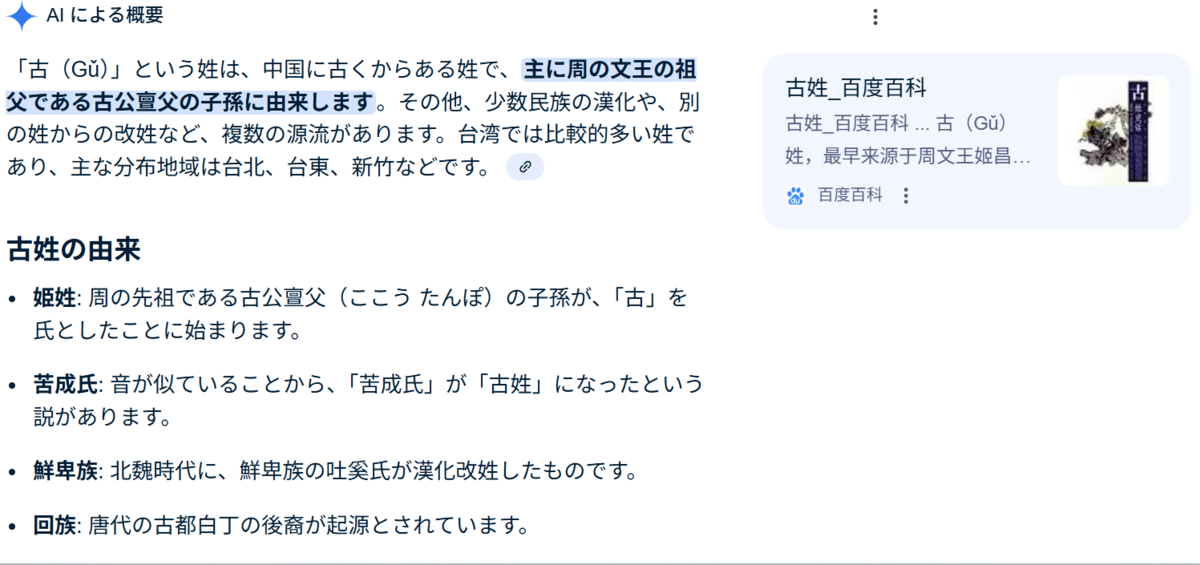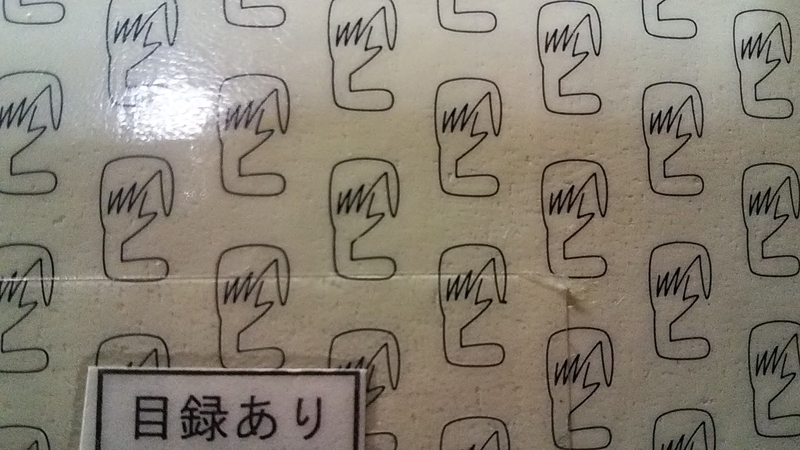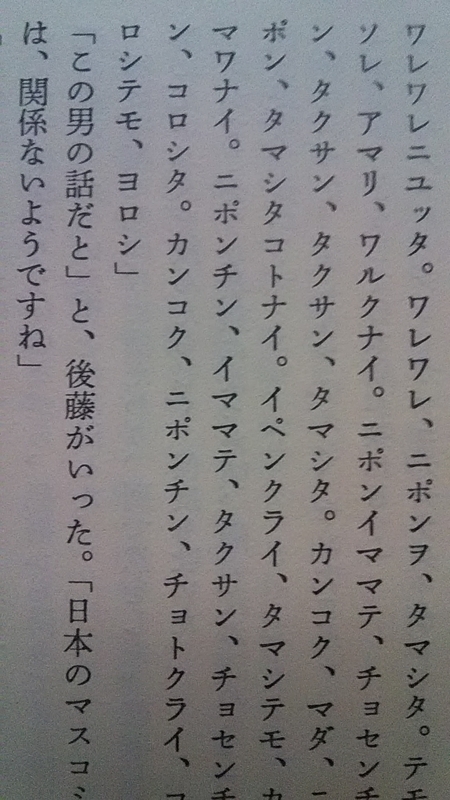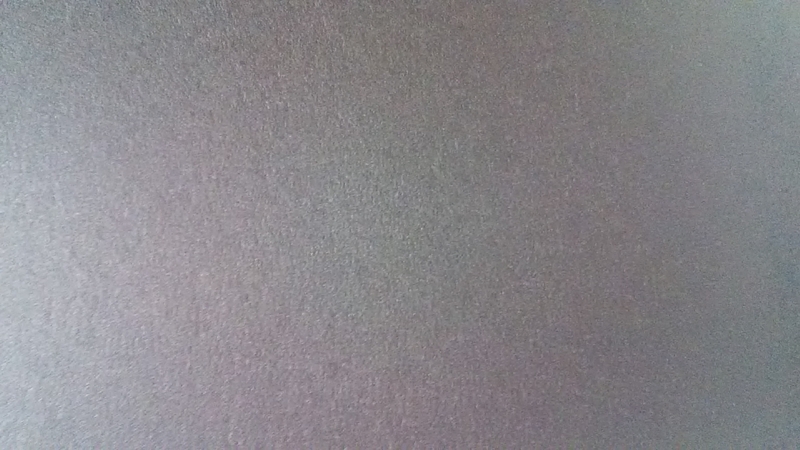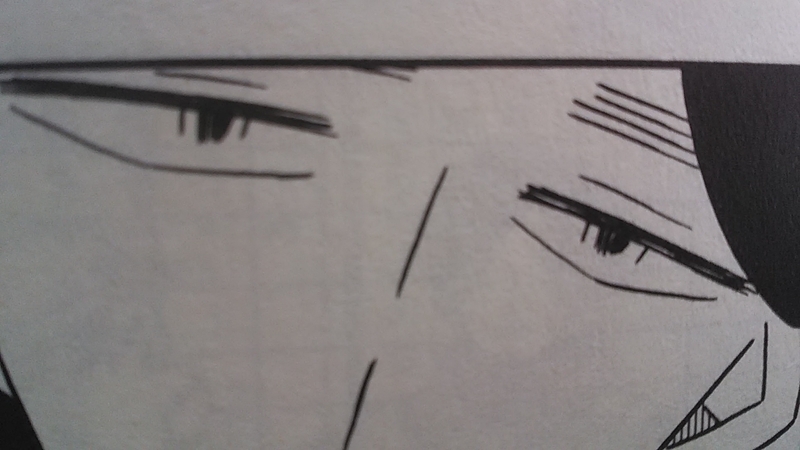AIはおそろしい。

どうしてそういうことになるのか。1989年生まれのトージョーサンが1965年1966年発表の作品をどないして書くねんて。
『堕地獄仏法』"Down in Hell Buddhism,"(「SFマガジン」昭和40年(1965年)8月号)
「王仏冥合の理念」「仏法民主主義」「〝国立〟戒壇」「天皇の法華経帰依」「神天上」「社参停止(しゃさんちょうじ)」「謗法罪」「一切の神社に神霊ましまさず」「次つぎに有名神社をぶち壊した」のっけからバンバン出ます。



「謗法罪」読めませんでした。「社参停止」にはルビ振ってあるのに、こっちにはなし。「ぼうほうざい」かと思った。
頁163
車から見える会館、公会堂、講堂、ホールなど、集会のできそうなほとんどの場所には、指導会の看板が立てられていた。
当時はこれもいろいろ諍いのタネだったんですかね。今は自前の会館が各地にあるので、バッティングすることはほとんどないと思います。むしろ、宗教法人で固定資産税とかがどうなのかは分かりませんが、ふつうに維持費だけでも大変そうだなと。少子高齢化ですから。

①次に、風流夢譚事件(1960年)をモデルにしたと思われる事件が出ます。「第三親衛隊」と「統制委員会」というのが出ます。前者は分かりますが、後者がなぜそういう名称なのかちょっと分からなかったです。戦後すぐの感覚を私が持ってないからでしょうか。
②その次に、法主というか猊下の鼻問題が、「王様の耳はロバの耳」な感じで出ます。これも、時代が変わってしまったのか、私には分かりにくかったです。当時は時事ネタで、みな近しい感覚を持ちえたのでしょうけれど。


分からない。戸田城聖サンは1958年におなくなりだそうです。為念。

ちなみにですけど、私も今回検索するまで、初代教祖というか、潮から希望コミックスとしてマンガ化された『牧口先生』(未読。石森章太郎画とカンチガイしてました。作者知らない人だった)のしとが、軍ににらまれて獄中死してるとは知りませんでした。PL教団の前身のひとのみち教団も徴兵拒否していたので非国民とそしられたそうですし、なかなか戦前に新興宗教やるのも大変だったと。仏教は積極的に翼賛で、日蓮宗のお坊さんはラジオで熱心にアジっていたそうなので、その辺から戦後の齟齬のタネが蒔かれていたのかも、とは蛇足。
「なんでホロコーストのユダヤ人が建国したイスラエルがガザを…」みたいな話でもないと思いますが、この小説では悪書は焚書で、全五百八十九種類約五千冊の本が焼かれます。新聞の見出しは「餓鬼! 因果応報! 勤行を怠った八百屋一家、突然の火事にて阿鼻大城の底に沈む!」など。

頁172
「正教歌壇・入選
大衆の福祉誓いて堂堂と
恍瞑党は駒を進めん
(第229部隊 広山元)」
「正教俳壇・入選
ラムネ噴きこぼれメーデー散会す
嘲りの糞まみれなる手摺りかな(暁汀)」
俳壇がさっぱり分かりませんでした。感覚がもう…
下記がこの小説のキモなのかな、という気がします。
頁173
「君は、自由主義者じゃなかったのか?」
「うん。だがマスコミ理論に関しては、少し考えが変わってきた。マスコミが自由すぎると混乱が大きい。マスコミが巨大になると、こんどはその巨大な力を自分自身の目的のために行使しはじめる。自由主義社会のマスコミ関係者たちは、反対意見を出さずに自分たち自身の意見を宣伝するようになる。資本主義では、マスコミは大企業に媚びてるから、しばしば広告主に編集内容を支配されてしまう。 マスコミは重要なものよりも、表面的でセンセーショナルなものにばかり注意をはらいがちだ。誰にでも喋らせるという面では、個人のブライヴァシー侵害という問題がおこる。嘘をつき、人を誹謗し、物ごとを歪める。だいいち、 資本主義社会のマスコミは、いわば企業家階級とでもいうような社会経済的な階級に支配されているから、新入りのものがマスコミ産業に接近することは、まず不可能だ。恍瞑党政権確立以前のマスコミの思想の自由は、危殆に顔していたんじゃないかな?」
「そんなことがあるもんか。現在と比較すりゃ、自由はいくらでもあったさ。たしかにそりゃあ、あの頃のマスコミは、あやふやな事実、まちがいだらけの事実、でたらめな事実を無茶苦茶に報道した。だけど僕は君よりも大衆を信頼するね。あのころの大衆は、社会の市場に充満しているいろんな思想の渦の中で、真理を探し求めはしなかっただろうか? (略)そりゃ、この相互作用は、時には混乱したかもしれないさ。生産的でなかったかもしれない。だけど、どう考えたって今みたいな権威主義的な命令よりは好ましかった。長い眼で見りゃあね」
「大衆って奴を、そんなに信じていいのかね? 僕は懐疑的なんだ。その証拠に、現在の大衆を見ろよ。わずか二、 三年で完全に頭の中の思想を入れ替えちゃってる。人間って奴はさ、だいたい理性を使うことを億劫がるんだ。そしてその結果は容易にデマゴーグや広告で釣る政治家や商人たちの餌食になる。精神的に怠惰だから、無分別に物ごとに盲従する。利己的な人間にあやつられるんだ」(略)
「現在アメリカでは」と彼が喋りはじめた。「社会で発言している大衆が、マスコミは社会に対して一定の基本的な機能を果たすよう責任を持たされているはずだといって、マスコミに一定の行動基準を要求しはじめているんだぜ。 自由には責任がつきものだからな。もしもマスコミが責任を考えない場合には、マスコミの基本的機能が果たされているかどうかを、何らかの別の機関が調べるべきだというんだ。アメリカみたいな資本主義国でさえ、こんな、社会的責任理論が発生してきているんだ」
「だけど日本でだって、マスコミ関係者は大体において自発的に責任と自由とをつなぎあわせていたじゃないか。倫理的な行動綱領を制定して、公共の利益に多少気を配りながらメディアを運営していたはずだ」
「うん。だけどそれは、彼らがそう考えた公共の利益というものにすぎなかったんだ。いいかい。マスコミに関する社会的責任理論は、伝統的な自由主義理論と比べて、自由の概念が基本的に異なっているんだ。自由主義理論は消極的な自由の概念から生まれたもので、その自由は外部制約 〈からの自由〉だった。社会的責任理論は、それとは逆の(略)「資本主義社会のマスコミは」また、和本が喋りはじめた。 「金儲け本位だった。特殊利益や、腐敗や、無責任に支配されていることが多かった。誤りがそのまま流され、訂正されなかったりした。娯楽も馬鹿げたものばかりだった。 ニュースにしても、ナマの事実の漫然たる寄せ集めだった。 それは認めるだろう?」
「まあそれはある程度認めるが」僕はしかたなしにいった。「しかし、だからといって全体主義がいいとはいえない」
「ところが現在の――つまり、恍瞑党政権下のマスコミはだな」彼は強引に話を押し進めた。「すべての相互矛盾的な傾向の全体を深く考える。そしてすべての社会的階級の生活の安定という、明確に規定された条件に還元するんだ。現在マスコミは、ある社会の思想を説明する場合の主観主義や恣意性を断固として排斥する。うん、そうとも」
「どうにでも説明はつくさ。でも具体的に行なわれていることは言論統制だ」
「具体的にはだ」彼の口調はますます熱っぽくなってきた。自分をそう信じこませようとしていら立っていた。「具体的には恍瞑党は、選挙で、国家業務の主要な地位に党の候補者―――つまり人間社会主義の建設に専心していて、一般大衆からいちばん広沢な信頼をうけている莫蓮正宗のもっともすぐれた信者の進出をはかるようにマスコミを助けるのだが、これは何も言論統制じゃない。もちろん党は、マスコミの仕事を検証はする。だけどそれは、やむを得ない誤りや欠陥を正すためなんだ。マスコミが政府の決定を発展させるのを助けるためなんだ。党の指令に合致しない記事が出るのを防ぐためだ。マスコミは大衆の支持を保証しなけりゃならないんだからな。それからまたマスコミが、 事業計画を発展させるばあい、党は指導を・・・・・・」
そのとき、いきなり電車通りでポンポン拳銃を撃ちあう(後略)
オチは正真正銘のディストピアなので、主人公とそのジョーカノほんとにかわいそう、という感じでした。ウソでもいいから自白すれば助かるというものでもない状況に追い込まれて拷問が始まって終わります。ホテルニュージャパンで拉致されるのですが、ホテル名が実名なのでなんじゃこりゃと思いました。横井英樹サンは別に学会と縁のある人でもないようで、名城大学の名誉教授の人がnoteに書いていたのですが、1963年にナベツネプロデュースで自民党副総裁大野伴睦サンと池田大作サンが二者会談をホテルニュージャパンでやって都知事選の票についてやりとりしたそうで、そういうことがあったので筒井サンは場所をそこに設定したのかなと思いました。
ここで描かれてることは、カルトであればあるほどじゅうぶん笑顔でおっぱじめる可能性のあることだと思いますが、これが学会と公明党によって引き起こされるという仮想未来に対し、知人のネトウヨの人もそうですが、けっこうまじめに首をタテにふる人がいるというのが、当時の時代、またそういう運動が熱狂的だった地方なのかなと思います。私は選挙の時公明党に入れてほしいという電話をかけてきた同級生もひとりしかいなかったような地方ですので、熱狂的な地区の話がなんとなくピンとこないまま、戦後の新興宗教も少子高齢化で、現在ゆっくり退潮期に入るという…
『末世法華経』"The Lotus Sutra of the apocalypse,"(「宇宙塵」昭和41年(1966年)2月号)
宇宙塵ということは同人誌発表。商業誌でないということは、もっと過激に書けるのかと思いきや、前作の方がヒドいです。二作目はおとなしめにしたけどどこも載せてくれなかったのかも。そして三作目はない。
グーグル翻訳は「末世」の英訳を"the latter days"としたのですが、検証すると、モルモン教がよく使う言い回しとのことでしたので、まあそれもなんだなと思って、アポカリプス(黙示録)にしました。

日蓮がタイムトンネルかなんかで現代にタイムスリップして、その後がやや強引なのですが、学会の講義会が代々木区民会館で開かれてるので、行ってみようということになり(強引だなあ)行くと、代々木だからか、共産党員と思われたりしてフルボッコにされて叩き出されるという。全集のこの巻のうしろのエッセーによると、筒井サンは上京して阪僑として原宿に居を構えたそうなので、それで代々木なのかと納得しました。原宿と代々木は隣ですもんね。
妊婦やタクシーの運転手への学会員の脅しが伝聞として出て来ますが、そういうことをするのは組織の末端のヤカラということにしています。気を使ってますね、前作より。
日蓮上人の生涯とか、学会の教えとの相違点など、よく調べたと思うんですが、その細かさが逆に一般読者にはどうでもいいという、そんな作品になっています。それにしても、これが日蓮宗だからまだいいものの、イスラム教のマホメットでやらなくて本当によかったと、筒井さんご本人も、サルマン・ラシュディ『悪魔の詩』が殺害のファトワを出され、邦訳した人が大学構内で刺殺された事件のさいにつくづくそう思ったのではないかと思います。古い事件ですが、いまだに衝撃的です。未解決だし、殺し方が回教徒独自の方法だし、容疑者出国してるし、捜査打ち切りだし。
『堕地獄日記』"Down in Hell Diary"(「SFマガジン」昭和40年(1965年)11月号)
エッセイです。『堕地獄仏法』を発表してから、どんなことがあったかをざっと書いてる。投書は封書が一通、ハガキ二通。自宅に電話一本。そんなもので済んだとか。また、学会の出してる活字媒体ではやはり批判の対象になったとか(掲載誌を叩く戦術)しかし、日蓮正宗の方なのかな、学会と対立する宗教団体からは、よくやったとべた褒めがもらえたとか。あと、平井和正がこの件にすごく関心をよせていたそうで、それは分かるのですが、SF作家には霊友会など他の新興宗教に近い人もほかにいたはずなので、平井和正サンだけというのはさびしいかなと思いました。でもほかの人は世代が下で、1965年にはまだ世に出ていなかったのかもしれない。
私は平井和正サンの『幻魔大戦』(角川文庫)全二十巻は読み終えたかどうかよく覚えてないのですが、新興宗教というのはこうやって盛り上がっていくのかと、今思い返すとよく分かる展開だったと思います。難病で見捨てられた子が奇跡で治るとか、その子の家族はアノミーで家も腐臭が漂っていたが、一度良い方にPDCAサイクルが回り始めるとどんどん生き生きしてきて血色もよくなって働き出して、とか。その後、どう停滞するかについては、半村良『岬一郎の抵抗』は『幻魔大戦』を念頭において、ああいうふうにはしたくないと思ったのかなあという感じに、角川版『幻魔大戦』は、教祖がおかくれになって(死んだわけではないがほんとにどっかに行ってしまう)ゴドーを待ちながら的展開の中で、新興宗教を渡り歩く宗教ゴロみたいのに牛耳られそうになると別のすごいパワーの人物がそれを跳ね返すも、そのパワーの人もやっぱり新しい取り巻きに取り巻かれてなんだかよく分からなくなる、俗世の人間から見えなくなる、みたいな展開、残された人々のただただ耐えて生きるその後の人生が描かれるという、読者の中に宗教二世がいて親以上に熱狂してたら、こういう展開に考えるところもあるだろうなという小説でした。いましろたかし『デメキング』は怪獣を待つ話ですが、『幻魔大戦』はメシアが来てどっかに行ってしまって待つ話ですので、後年いましろたかしが『原発幻魔大戦』なんてエッセーマンガを描いたのも、影響下かなあと思ったり。
いちおう全集二巻のほかの話もぜんぶ読んだので、この後感想を書きます。以上